特定技能1号を受け入れる企業には「支援計画書」の作成と実行が義務付けられています。本記事では、宿泊業における支援計画書の必要性と、その作成方法やメリットを詳しく解説します。外国人材を受け入れる際の手続きや注意点を把握し、スムーズに採用を進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
なぜ宿泊業で「支援計画書」が必要なのか?
宿泊業は24時間体制で稼働し、繁忙期と閑散期の差が大きいという特徴があります。日本語や生活環境に不慣れな外国人が、夜勤やシフト勤務などの特殊な就業条件に対応するのは簡単ではありません。そこで、受け入れ企業が作成する「支援計画書」が重要になります。
特定技能1号の場合、初めて日本に来る外国人や滞在歴が浅い外国人が多いため、生活や業務面での支援が不可欠です。支援計画書を適切に作成し、実際の支援内容をしっかり実行することで、外国人労働者が早期に職場へ馴染み、安心して働ける環境を整えられます。
「支援計画書」とは?
支援計画書とは、特定技能1号を雇用する際に必要となる「職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援」をどのように実施するかまとめた書類です。作成するのは受け入れ機関(企業)で、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などの際に提出が必須です。
計画書には、具体的な支援内容や担当者、支援方法、スケジュールなどを詳しく記載します。この支援計画が不十分だと、申請が不許可になる可能性があります。また、支援計画書の実行を自社で行うだけでなく、登録支援機関に委託して実施することも可能です。
「支援計画書」で義務付けられている10項目
①事前ガイダンス
雇用契約を結んだ後、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請の前に行います。労働条件や入国手続き、日本のルール、保証金徴収の有無などを対面またはテレビ電話で説明します。外国人が十分に理解できるまで丁寧に対応することがポイントです。
②出入国時の送迎
入国時は空港から事業所または住居までの送迎を手配します。帰国時も保安検査場まで同行し、確実に帰国できるようサポートする必要があります。深夜や早朝のフライトが多い宿泊業の場合、特に配慮が大切です。
③住居確保・生活に必要な契約支援
銀行口座や携帯電話、ライフライン契約などの手続き支援を行います。必要に応じて連帯保証人になる、社宅を提供するなど、外国人が安心して生活を始められる環境づくりが求められます。
④生活オリエンテーション
日本でのマナーや公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明します。宿泊業は地域とのつながりも重要です。周辺の買い物施設や交通ルートなど、実際の生活で困らないよう案内するとスムーズです。
⑤ 公的手続きへの同行
住民登録や社会保険、納税などの手続きに必要な情報を提供し、場合によっては同行します。書類作成の補助も行い、外国人が言語や書式で困惑しないようにすることが大切です。
⑥ 日本語学習の機会の提供
宿泊業は接客が多いため、ある程度の日本語力が求められます。日本語教室やオンライン学習など、多様な方法を紹介し、必要に応じて費用補助を行う場合もあります。日本語力向上はトラブル防止やサービス品質向上にも繋がります。
⑦相談・苦情対応
夜勤や不規則なシフトなどでストレスを抱えやすい業界です。勤務条件や人間関係などの悩みに対し、外国人が十分に理解できる言語で相談を受け付け、適切に対応しましょう。相談窓口を明確化しておくと安心です。
⑧ 日本人との交流促進
自治会や地域イベントへの参加を促し、日本人との交流をサポートします。職場以外にも地域の行事に参加することで、日本の生活や文化を深く理解してもらえます。
⑨ 転職支援
企業都合で解雇が必要になった場合、次の転職先を探す手伝いや推薦状の作成を行います。やむを得ない事情で雇用継続が困難になった場合でも、責任をもってサポートする姿勢が求められます。
⑩定期的な面談・行政機関への報告
3か月に1回以上、本人や上司と面談を実施します。労働条件の違反やトラブルがあれば行政機関へ通報する必要があります。早期に問題を把握し、適切に対処できるようフォロー体制を整えてください。
「支援計画書」の作成で得られるプラス効果
支援計画書は義務ですが、作成・運用をしっかり行うことで、次のようなプラス効果が期待できます。
- 在留資格申請がスムーズ:十分な支援体制が整っていると判断されれば、許可が下りやすくなります。
- 職場定着率の向上:慣れない日本での生活を支援することで、外国人材が長く働きやすい環境を実現できます。
- 業務トラブルの予防:コミュニケーション不足や生活上のトラブルを未然に防ぎ、企業側のリスク低減にもつながります。
- 企業イメージの向上:外国人を積極的に受け入れ、適切にサポートする姿勢が社内外の評価を高めます。
支援計画書の作成方法
- 様式の入手
出入国在留管理庁のホームページから、特定技能1号に関する支援計画書の参考様式をダウンロードします。 - 外国人の情報を入力
氏名、国籍、生年月日などを正確に記入します。 - 受け入れ企業・担当者の情報
支援責任者や支援担当者の氏名、役職、連絡先を記入します。併せて支援担当者が公正にサポートできる体制になっているかも合わせてチェックしましょう。 - 支援内容の具体的記載
義務的支援10項目それぞれについて、実施期間や方法、担当者などを明確に書き込んでください。 - 登録支援機関の利用有無を記載
委託先がある場合は、契約内容や登録支援機関の詳細を記入し、担当範囲を区別します。 - 本人への説明・署名
計画書の内容を外国人が十分に理解できる言語で説明し、署名を得ます。同意の証明は入管手続きでも重要です。
支援計画書の作成は依頼できるの?
「支援計画書」の作成は、登録支援機関や行政書士・社労士に委託できます。登録支援機関は外国人雇用の実績や専門知識を持っているので、スムーズな運用が期待できます。言語面でのトラブルや細かな法改正への対応にも強く、支援計画書の内容が実態に合わないといったリスクを抑えられるのも魅力です。
行政書士・社労士は法改正にも詳しく、在留資格申請や労務管理までサポート可能です。自社対応が難しい場合はこれらの専門家へ依頼し、負担を軽減しましょう。ただし、費用や要件の確認も忘れずに行うことが大切です。
F&Qよくある質問
Q1. 支援計画書はどの書類と一緒に提出するのか?
A. 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請など、特定技能1号に関する在留諸申請時に提出します。申請書類一式と同時に提出しないと審査が進みませんので、準備をしっかり行いましょう。
Q2. 支援計画書の有効期限はあるのか?
A. 支援計画書自体には特定の有効期限はありません。ただし、支援内容に変更があった場合は14日以内に入管へ届け出る必要があります。実態と計画書が一致していないと、在留資格の更新に影響が出る可能性があるため注意が必要です。
Q3. 一度作成した支援計画書は再利用できるのか?
A. 外国人の国籍や業務内容、雇用条件などが同じなら、基本的な部分を再利用できます。しかし、支援対象者の言語レベルや具体的な配属先などが変わる場合は、その都度記載内容を調整し、最新版を作成・提出しましょう。
Q4. 事前ガイダンスをメールだけで行っても大丈夫ですか?
A. メールや書面のみのやり取りは原則不可とされています。対面やテレビ電話など、相手の表情を確認できる方法で実施しなければなりません。特定技能外国人が十分に理解しているかを確かめることが大切です。
Q5.支援対象となる特定技能外国人が複数名いる場合、支援計画書はどう提出すればよいですか?
A.支援対象者が複数いても、支援内容が同じなら、1つの支援計画書と第3-2号(別紙)を提出すれば個別作成は不要です。
ただし、全員に支援計画書を渡し、署名をもらう必要があります。
支援内容が異なる場合は、個別に作成・提出が必要です。
※参照元:特定技能関係の申請・届出様式一覧「第1-17号 1号特定技能外国人支援計画書」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
Q6.特定技能2号は支援計画書が必要ですか?
A.特定技能2号には支援計画書の作成義務はありません。
1号特定技能外国人は滞在歴が浅く、職場や生活に慣れるための支援が必要ですが、2号特定技能外国人は日本での生活が安定しているとみなされるため、支援は不要とされています。
まとめ
特定技能1号の外国人を受け入れる際には、「支援計画書」の作成と実行が義務付けられており、安心して働ける環境づくりに欠かせません。宿泊業特有の就業条件に対応するためにも、計画的な支援が重要です。適切な計画書の運用は、在留資格申請の円滑化や職場定着率の向上にもつながります。専門機関への委託も検討しながら、確実な対応を進めましょう。
当サイトでは、外国人材の雇用を検討しているホテル・宿泊業の施設運営に関わる法人向けに、国内ホテルでの成功事例・複雑な制度や手続きの解説・宿泊業に特化した外国人材紹介サービス(人材紹介会社)の比較などのコンテンツを掲載していますので、是非お役立てください。
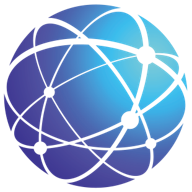 Global Talent Station
Global Talent Station