口約束はNG!外国人雇用には契約書が必須
労働条件通知書が必要な理由
労働条件通知書は、企業が労働者と雇用契約を結ぶ際に必ず発行しなければならない法的書類です。労働基準法第15条に基づき、発行が義務付けられており、違反した場合、企業は30万円以下の罰則を受ける可能性があります。
就業規則とは異なり、労働条件通知書は労働者ごとに個別の条件を明示するものであり、企業は就業規則を設けていたとしても別途発行しなければなりません。
労働条件通知書の目的
この通知書の目的は、労働者の権利を保護し、雇用条件の認識違いによるトラブルを未然に防ぐことです。例えば、面接時に提示された給与や勤務条件と実際の雇用契約が異なる場合、労働者が不利益を被ることがあります。
労働条件通知書を交付すれば、雇用条件の透明性が確保され、労使間の信頼関係を構築することが可能になります。さらに、企業にとっても、契約内容を明確にすることで労働者とのトラブルを防ぎ、適正な労務管理を行うための証拠として機能します。
外国人労働者における特別な配慮
外国人労働者を雇用する際には、契約内容を正確に理解してもらうことが重要です。厚生労働省のサイトでは、英語、ベトナム語、中国語などの多言語対応の労働条件通知書の雛形が提供されています。これを活用することで、言語の壁による誤解を防ぎ、より円滑な雇用関係が築けます。
※参照元:厚生労働省「労働基準関係リーフレット」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
雇用契約書と労働条件通知書の違い
雇用契約書と労働条件通知書は、どちらも給与や職務内容を記載する点では共通していますが、内容の扱いが異なります。労働条件通知書は、企業が労働者に対して一方的に労働条件を知らせるもので、労働基準法で発行が義務付けられています。一方、雇用契約書は、企業と労働者が契約内容に合意し、署名・押印をして成立する書類です。
どちらも必要?片方だけでいい?(よくある誤解を解説)
労働条件通知書は労働基準法で発行が義務付けられており、企業は必ず作成しなければなりません。違反した場合には罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。
一方で、雇用契約書の作成は法的義務ではありませんが、外国人労働者を雇用する場合には労働条件通知書だけでは不十分なことが多いため、双方の合意を明確にするために作成が推奨されます。
雇用契約を交わしているから労働条件通知書は発行しなくてもいいわけではありませんので、必ず発行しましょう。
外国人雇用契約書の注意点
① 在留資格(ビザ)に適合した契約内容であること
外国人労働者は、在留資格(ビザ)によって働ける業務が決まっており、契約内容が適合していない場合、違法雇用となる可能性があります。そのため、労働条件通知書には、在留資格に適合した業務内容を明確に記載しなければなりません。
例えば、エンジニアの場合は「システム開発業務」と具体的に記載し、労働時間や休日が入管法の基準を満たしていることを確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務ビザではホワイトカラー職種に限定され、単純労働は認められません。特定技能ビザでは許可された業種・職種の範囲内で業務を行う必要があり、技能実習ビザでは実習計画と契約内容が一致していることが求められます。
② 母国語での説明が推奨される
労働基準法では「労働条件を明確にすること」を義務付けており、外国人労働者が理解できる言語で説明することが望ましいとされています。
そのため、労働条件通知書は日本語に加え、英語やベトナム語、ネパール語、ミャンマー語など外国人が理解しやすい言語で作成することが推奨されます。また、重要な条項については翻訳をつけるか、口頭で説明を行い、労働者が内容を理解した上でサインをもらうことが大切です。
③ 外国人向けの特有の手当・費用負担に関する記載
外国人の受け入れには渡航費、ビザ申請費、住居費などの費用が発生するため、これらの負担者を明記することが求められます。特定技能の場合は、支援計画の内容と契約が一致しているかを確認する必要があります。
具体的には、渡航費や住居費を企業または労働者のどちらが負担するのか、帰国時の費用負担の有無、特定技能の場合に企業が提供する生活サポートの内容を契約書に記載し、明確にしておくことが重要です。
④ 技能実習生・特定技能の「雇用契約の解除」には制約がある
技能実習生や特定技能外国人は、雇用契約を解除する際に特別なルールがあります。特定技能の場合、企業が解雇を行う際には「30日前の通知」と「転職支援の義務」が求められます。
技能実習の場合、実習計画と一致しない解雇は違反となり、企業にペナルティが課せられる可能性があります。そのため、解雇の際には入管法に基づき適切に対応することを契約書に記載し、退職や解雇の際の通知期間を明確に定めておくことが重要です。
⑤ 外国人技能実習機構・出入国在留管理庁への報告義務
技能実習や特定技能の外国人を雇用する場合、契約内容を所定の機関に提出・報告する義務があります。技能実習の場合は外国人技能実習機構へ報告し、特定技能の場合は出入国在留管理庁への提出が必要となります。
適切な報告を行うことで、企業の雇用管理が適正であることを証明し、法令違反を防ぐことができます。
停止条件付雇用契約とは?ビザ取得前の雇用のポイント
外国人労働者を雇う際には、「在留資格が取れたら雇用契約が有効になる」と契約書に書くことが重要です。例えば、「日本政府が在留資格を許可しなかった場合、この契約は無効になる」と明記することで、企業が違法な雇用を避けることができます。この仕組みは「停止条件」と呼ばれ、条件が満たされたときに契約が成立します。
特に、留学生が働くためのビザに変更する場合は、「在留資格変更が許可されなかったら契約は無効」と記載することが望ましいです。これにより、企業は予期せぬトラブルを避け、適正な雇用を行っていることを証明できます。
契約書には、在留資格が取れなかった場合の対応を明記し、労働者にもわかりやすく説明することが大切です。専門的な言葉ではなく、「在留資格が取れなかった場合、この契約は無効になります」といったシンプルな表現で、口頭でも伝えるようにしましょう。
労働条件通知書の作成方法
労働条件通知書には決まった書式はありませんが、必要な項目を網羅し、不備のない内容にすることが求められます。企業独自のフォーマットを作成することも可能ですが、作成に不安がある場合は、厚生労働省のホームページから提供されているフォーマットを活用しましょう。
労働条件通知書には、業務内容、労働時間、給与、休日、契約期間などの基本的な情報を明記し、労働者が条件を正しく理解できるように工夫することが重要です。また、日本語が不慣れな外国人労働者には、英語や母国語での補足説明を加えましょう。
※参照元:厚生労働省「外国人労働者向けモデル労働条件通知書(入力可能)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html
まとめ
外国人労働者の雇用においては、労働条件通知書の適切な作成が不可欠です。発行しない場合、企業は法的な罰則を受けるだけでなく、労働条件の認識違いによるトラブルが発生する可能性があります。また、日本語に加え、英語や母国語での説明が推奨されており、外国人労働者が契約内容を正しく理解できるような配慮も必要です。
さらには、外国人雇用の契約書日本人以上に慎重な対応が必要で、手続きのミスは、ビザ発行不可や労務トラブルのリスクも高まります。「すべて自社で対応するのは大変」と感じたら、外国人材紹介会社の活用も有効です。
これらの企業は、企業のニーズに合った人材を紹介し、雇用契約の作成や在留資格の取得手続き、労務管理のサポートを提供します。特に、採用経験が少ない企業にとっては、専門的なサポートを受けることで、手続きの負担を軽減し、適正な雇用管理を実現できるでしょう。
当サイトでは、外国人材の雇用を検討しているホテル・宿泊業の施設運営に関わる法人向けに、国内ホテルでの成功事例・複雑な制度や手続きの解説・宿泊業に特化した外国人材紹介サービス(人材紹介会社)の比較などのコンテンツを掲載していますので、是非お役立てください。
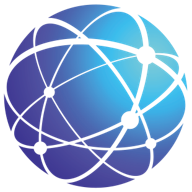 Global Talent Station
Global Talent Station
