介護業界における外国人採用は、近年ますます注目を集めています。特に人手不足が深刻な状況の中、外国人の介護スタッフの受け入れは有効な解決策のひとつです。
しかし、受け入れ状況や在留資格についての理解が不十分なまま採用を進めると、後々トラブルになりかねません。
この記事では、介護施設で外国人を受け入れるメリットや課題点、日本で受け入れ可能な介護関連の在留資格などをご紹介します。
まずは現状把握を!外国人の介護スタッフの受け入れ状況
介護業界では慢性的な人手不足が深刻化しており、外国人の介護スタッフの受け入れが急速に拡大しています。2024年10月末時点で、日本国内の外国人労働者数は2,302,587人で、外国人労働者の届出が義務化されてから過去最多となりました。
2,302,587人のデータを在留資格別に見てみると、外国人労働者数が多い資格の上位3位は以下の3つです。
- 専門的・技術的分野の在留資格…718,812人(31.2%)
- 身分に基づく在留資格…629,117人(27.3%)
- 技能実習…470,725人(20.4%)
上位3資格のうち、「専門的・技術的分野の在留資格」と「技能実習」は介護業界で働くことができる在留資格です。そのうち「専門的・技術的分野の在留資格」は前年比20.6%増で、外国人労働者の届出義務化後初めて最多となりました。
外国人労働者の国籍別では、ベトナムが最も多く570,708人(全体の24.8%)、次いで中国が408,805人(同17.8%)、フィリピンが245,565人(同10.7%)となっています。
この背景には、特定技能や技能実習といった新たな在留資格の導入により、外国人が介護業界で働きやすくなったことが考えられます。
外国人の介護スタッフを採用するメリットと課題を見ていこう!
続いて、介護事業者が外国人を採用するメリットと課題を整理します。
採用メリット
人手不足の解消
介護業界では慢性的な人手不足が続いており、日本人の採用はかなり難しくなりました。そこで外国人を介護スタッフとして採用することで人手が増え、現場の負担を軽減できます。
地方の施設でも採用が可能
外国人を介護スタッフとして採用する場合、採用地域の制限はありません。そのため、日本人の介護職員が集まりにくい地方でも、外国人なら条件次第で採用しやすいです。
海外進出を目指すときの助けになる
介護施設を運営する事業者によっては、将来海外にも事業所を展開したいと考えるところもあるでしょう。その場合、壁となるのが言語、現地の法律や習慣などです。
事業所展開を目指す国や地域出身、あるいは現地をよく知る外国人を採用することで、海外進出の際に大きな助けとなるかもしれません。
外国人を採用した介護施設の事例
実際に外国人を採用した介護施設はなぜ採用を決めたのか、採用した結果どのようなメリットがあったのか、事例をご紹介します。
事例1:特別養護老人ホームでの外国人採用例
- 日本人の採用がかなり厳しく、外国人採用に方向を転換した
- 採用後、職員の急な欠勤に対応できるようになったり、平均残業時間の削減や年間休日の増加などができた
- 採用前に懸念していた「外国人スタッフと利用者間のトラブル」もなく、素直で勉強熱心な人ばかりで、今や立派な即戦力になっている
参照元:STAFF PLUS(https://tokuteiginou.staffplus.co.jp/case/yoneyama-no-sato)
事例2:社会福祉法人(特別養護老人ホーム運営法人)の外国人採用例
- いずれ日本人スタッフだけでの施設運営が困難になると予測し、将来に向けて外国人採用を決めた
- 採用当初の現場では戸惑いの連続だったが、外国人採用の責任者が率先して外国人スタッフとコミュニケーションを図り、次第に他のスタッフとも打ち解けられるようになった
- 採用した外国人はみんな真面目で覚えが早く、施設利用者とも良好な関係が築けている
参照元:外国人採用サポネット(https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/interview/4670)
外国人採用時に申請可能な助成金もチェック!
新しく人を採用するときは採用コストがかかりますが、実は外国人を採用するときに申請可能な助成金があることをご存知でしょうか。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)は、外国人が長く安心して働けるように配慮した職場環境を整備する事業主に対して、経費の一部を助成する制度です。
助成を受けられる要件と受給額をまとめました。
助成を受けられる要件
(1)外国人労働者を雇用している事業主であること
(2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
※下記の1および2の措置に加え、3〜5のいずれかを選択すること。
- 雇用労務責任者の選任
- 就業規則等の社内規程の多言語化
- 苦情・相談体制の整備
- 一時帰国のための休暇制度の整備
- 社内マニュアル・標識類等の多言語化
(3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
受給額
(1)助成を受けられる要件をすべて満たした場合、支給対象経費の合計額に助成率をかけた額が支給されます。
- 賃金要件を満たしていない場合…支給対象経費の1/2(上限額57万円)
- 賃金要件を満たす場合…支給対象経費の2/3(上限額72万円)
(2)支給対象となる経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家などに対して支払った以下の経費が対象です。
- 通訳費(外部の機関または専門家などに委託をするものに限る)
- 翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
- 翻訳料(外部の機関または専門家などに委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類などを多言語で整備するのに要する経費を含む)
- 弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
- 社内標識類の設置・改修費(外部の機関または専門家などに委託をする多言語の標識類に限る)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)は、外国人を雇用する事業主に対して、各種訓練(※)にかかった経費や訓練期間中に外国人へ支払った賃金の一部を助成する制度です。
(※)職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練、厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練、非正規雇用労働者を対象とした正社員化を目指す訓練。
| 訓練種別 | 人材育成訓練 |
| 種類 | OFF-JT |
| 賃金助成額 | 760円 (380円) 960円 (480円) |
| 経費助成率 | 45% (30%) ※1 60% ※2 70% ※3 |
| OJT実施助成額 | ー |
| 訓練種別 | 認定実習併用職業訓練 |
| 種類 | OFF-JT |
| 賃金助成額 | 760円 (380円) 960円 (480円) |
| 経費助成率 | 45% (30%) 60% (45%) |
| OJT実施助成額 | ー |
| 訓練種別 | 認定実習併用職業訓練 |
| 種類 | OJT |
| 賃金助成額 | ー |
| 経費助成率 | ー |
| OJT実施助成額 | 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) |
| 訓練種別 | 有期実習型訓練 |
| 種類 | OFF-JT |
| 賃金助成額 | 760円 (380円) 960円 (480円) |
| 経費助成率 | 60% ※2 75% ※2 100% ※3 |
| OJT実施助成額 | 10万円 (9万円) 13万円 (12万円) |
| 訓練種別 | 有期実習型訓練 |
| 種類 | OJT |
| 賃金助成額 | ー |
| 経費助成率 | ー |
| OJT実施助成額 | 20万円 (11万円) 25万円 (14万円) |
※「賃金助成額」と「OJT実施助成額」の見方…上段:基本金額 下段:賃金要件などを満たす場合の金額
賃金助成額の( )内の金額…1人1時間あたりの金額
OJT実施助成額の( )内の金額…1人1コースあたりの金額
※1:正規雇用労働者などへ訓練を実施した場合の助成率
※2:非正規雇用の場合の助成率
※3:外国人労働者が正社員となった場合の助成率
※参照元:厚生労働省 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html)
※参照元(PDF):厚生労働省 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)のご案内(https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001325360.pdf)
募集時期や申請先、申請書類などの詳細は、厚生労働省の公式サイトでご確認ください。
採用における課題
在留期限の問題
外国人が日本で介護スタッフとして働くための在留資格は4種類ありますが、一部の在留資格は一定期間を過ぎると帰国しなければならず、長期的な雇用が難しくなります。
ただし要件をクリアすると別の在留資格に切り替えて期限を延長できることもあるため、長期雇用を計画する場合はそうしたサポートができる体制も考えておきましょう。
日本語能力の課題
日本に入国する外国人は基本的に一定の日本語能力をクリアしていますが、業務上の専門用語や日常会話などを採用当初から難なく理解することは難しいです。
一緒に業務を行うスタッフ同士のコミュニケーションはもちろん、利用者さんやそのご家族とのコミュニケーションが円滑に取れない場合、業務遂行に支障をきたしてしまいます。
日本語能力の課題解決には、外国人スタッフが日本語を学ぶ機会を継続できるような体制を整えることが重要です。
離職リスク
外国人は転職に対するハードルが低いため、せっかく採用してもすぐ辞めてしまう可能性も否めません。また、日本語能力の低さや周りとのコミュニケーション不足で孤独に感じ、離職を申し出るケースもあります。
介護事業者がかけた採用コストや労力を無駄にしないためにも、長期的な雇用を見据えたフォローが必要です。
外国人の介護スタッフを雇用できる在留資格の選び方
外国人の介護スタッフの採用には、目的や施設の方針に応じた適切な在留資格の選定が重要です。
日本で外国人が介護スタッフとして働くことが認められている在留資格は「介護」「特定活動(EPA介護福祉士)」「技能実習」「特定技能1号」の4種類です。
長く活躍を希望するなら在留資格「介護」
在留資格「介護」は、介護福祉士の国家試験に合格することで取得可能です。日本語能力や介護スキルが高い人材が多く、長期的な雇用が可能ですが、取得のハードルは高めです。
特徴
- 介護福祉士の国家資格を取得した外国人が対象
- 在留期間更新に制限がなく、長期間の就労が可能
- 家族帯同が認められており、外国人スタッフの離職リスクが低く定着しやすい
整った制度での育成なら「特定活動(EPA介護福祉士)」
「EPA介護福祉士」は、日本と特定国(インドネシア、フィリピン、ベトナム)の経済連携協定に基づく受け入れ制度です。こちらも日本語能力が高い人材が多いため、コミュニケーションを取りやすく業務を円滑に進めやすいでしょう。
なお、特定活動の在留資格を持つ外国人は、日本に入国して4年目になると介護福祉士の国家試験受験が義務付けられています。
合格すると引き続き働いてもらうことができますが、不合格の場合は在留期間満了に合わせて帰国しなければいけない点にご注意ください。
特徴
- 看護・介護の教育を受けた外国人が対象
- 日本語能力が比較的高い
- 4年目に介護福祉士国家試験の受験が必須
受け入れのしやすさなら「技能実習」
技能実習は、外国人が日本の技術を母国に持ち帰ることを目的とした制度です。「介護」や「特定活動」と比べると受け入れ条件のハードルが低く受け入れやすいですが、研修や就労制限があります。
技能実習に該当する外国人は、一定の条件を満たすと在留資格を「特定技能」に切り替えることが認められ、切り替え後は在留期限をさらに5年延長して働いてもらうことが可能です。
特徴
- 本国への技能移転が目的
- 最長5年間の実習が可能(技能実習2号、3号への移行条件あり)
- 特定技能への移行でさらに5年間の就労が可能(合計10年)
幅広い業務に従事してほしいなら「特定技能1号」
特定技能1号は、2019年に新設された在留資格で、技能や日本語能力を計測する試験に合格すれば取得できます。
特定技能1号は、他の在留資格と比べると携われる介護業務の幅が広く、さらに業務制限も少ない点がメリットです。
そして特定技能1号の外国人は、1人で夜勤をすることも可能。既存スタッフだけだと個々の事情で夜勤に入れる人員が足りないとお悩みの介護施設でも、特定技能1号の外国人を採用することで即戦力としての活躍が期待できます。
特徴
- 最長5年間の就労が可能
- 介護保険施設やグループホームなど幅広い職場で勤務可能
- 1人夜勤が可能で即戦力として活躍できる
- 技能実習からの移行が可能
ここ数年で急激な増加?特定技能1号受け入れの流れ
特定技能1号の受け入れは、採用予定の外国人が国内在住か海外在住かで流れが異なります。
日本在住者の外国人の場合
- 日本語能力試験と特定技能試験に合格、または技能実習2号を良好に修了する
- 在留資格変更許可申請
- 介護施設へ入職する
日本在住の外国人を特定技能1号として受け入れる場合は、入国前に介護施設側が行うべき手続きはいりません。
海外在住者の外国人の場合
- 日本語能力試験と特定技能試験に合格
- 在留資格認定証明書交付の申請を行う
- 入国
- 介護施設へ入職する
海外に住んでいる外国人を特定技能1号として受け入れる場合、受け入れ機関となる介護施設側が在留資格認定証明書の交付申請を行います。
以下に、特定技能の在留資格を申請する際に必要な書類をまとめました。
- 表紙 ・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
- 在留資格認定書交付申請書
- 特定技能外国人の報酬に関する説明書
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件の写し
- 特定技能所属機関概要書
- 登記事項証明書
- 業務執行に関与する役員の住民票の写し
- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書
- 労働保険料納付証明書
- 社会保険料納入状況回答票または健康保険
- 厚生年金保険料領収証書の写し
- 税務署発行の納税証明書
- 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年分) など
この他にも、外国人の健康診断書や1号特定技能外国人支援計画書など、用意する書類はたくさんあります。
これらの書類を揃えて日本の出入国在留管理局に申請し、在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書は海外で日本への入国準備を行っている外国人へ送付します。
母国で在留資格認定証明書を受け取った外国人には、それを現地の日本大使館または日本領事館へ持っていき、ビザを発給してもらうよう伝えてください。日本と海外それぞれで申請を行うため、外国人が入国するまでに数ヶ月かかります。
申請書類に不備があればその分入国の時期もずれるので、申請前のチェックはしっかり行いましょう。
なお、「一定の事業規模があり、過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関」に該当する場合は、申請書類の一部を省略することが認められています。
申請書類の一部省略が対象となる機関
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 電子届出システムに利用者登録をしている
出入国在留管理庁の公式サイトに、特定技能の外国人を受け入れる際に必要な書類や詳しい条件、留意事項などが掲載されていますので、必ずご確認ください。
参照元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html)
まとめ
外国人を介護スタッフとして採用することは、介護業界の人手不足を解消する有効な手段です。ただ、単純に人手がほしいからと安易に採用を決めるのではなく、採用するメリットや新たに起きる可能性がある課題、在留資格の違いと申請方法などを理解しましょう。
そうすることで、介護施設で働くスタッフの負担を減らすことが可能です。
外国人の介護人材採用についてお悩みの方におすすめのサービスも紹介していますので、ぜひご覧ください。
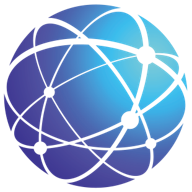 Global Talent Station
Global Talent Station

