介護業界で進む人手不足の解消策として、近年注目度が高まっている外国人介護人材の受け入れ制度。ここでは外国人を介護人材として受け入れる際に知っておくべき4つの制度について解説します。
4つもある?外国人介護人材の受け入れの仕組み
外国人の介護人材を受け入れる制度には、以下の4つがあります。
1.EPA(経済連携協定)
EPA(Economic Partnership Agreement)とは、日本と特定の国との経済連携協定に基づく制度です。対象国から受け入れた外国人の介護福祉士候補者は、介護福祉士養成施設(※)または介護施設などで実務を学びながら、介護福祉士の国家試験合格を目指します。
(※)介護福祉士養成施設…介護福祉士の養成課程を持つ大学・短大や、介護福祉士の資格取得を目指した専門教育を行う専門学校などのこと。
受け入れ先が介護福祉士養成施設の場合は2年以上、介護施設の場合は3年以上学ぶことが必須です。
指定の研修期間(または実習期間)終了後、外国人は介護福祉士の国家試験を受験します。晴れて合格した後は在留期間を更新して引き続き介護福祉士として働くことが可能です。
ただし国家試験不合格の場合、外国人の方は帰国しなければなりません。
またEPAの受け入れ対象国はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国に限られていることにもご注意ください。
2.在留資格「介護」
在留資格「介護」は、外国人留学生または技能実習生として日本に入国後、所定の施設で定められた期間実務経験を積んだり研修を受けたりする制度です。
入国後は介護福祉士養成施設で2年以上学ぶ、あるいは介護施設などで3年以上実務経験を積んだり研修を受けたりします。
こちらもEPAと同じく、受け入れた外国人が介護福祉士の国家試験に合格すると、日本の介護施設で引き続き働くことが可能です。
なお、EPA・在留資格「介護」は、どちらかの制度に該当する外国人が介護福祉士の国家試験に合格すると、在留期間の更新回数制限なしで働けて家族(配偶者と子)も一緒に日本へ帯同することも認められる点も特徴です。
3.技能実習
技能実習制度は、発展途上国の人材が日本で介護の技術や知識を学び、母国の発展に貢献することを目的とした制度です。2017年に介護分野が対象に追加されて以降、多くの事業者がこの制度を活用しています。
技能実習は、外国人が最大5年間の在留期間中に、事前に策定された実習計画に基づいて具体的な介護技術やコミュニケーション能力を実践的に習得する仕組みです。
この実習計画の認定は、厚生労働省が所管しており、具体的な手続きは外国人技能実習機構(OTIT)が担当しています。
そのため教育内容が実務に即したものとなり、外国人が実習生として短期間で現場のことを学ぶため、実務を覚えたあとは即戦力として活躍することが期待できます。
また、実習計画が事前に詳細に構築されているため、事業者が独自にカリキュラムを作成する負担を軽減できるのも特徴です。
ただし、技能実習生は実習終了後に帰国しなければならないため、5年以上の長期雇用を前提で考える場合はご注意ください。
4.特定技能1号
特定技能1号は2019年に新設された在留資格で、介護分野でも積極的に活用されています。この制度では、技能水準や日本語能力水準を試験などで確認した外国人が採用人材の対象となります。
他3つの制度と違うのは、試験を受けるタイミングが日本への入国前ということ。
母国で試験を受けて日本へ入国後、介護施設などで5年働き、その後帰国します。
4つの制度の違いまとめ
EPAや在留資格「介護」は、介護福祉士の国家試験に合格すると5年以上の就労が可能なので、しっかり育てて長期的な雇用を見据えたい介護事業者に向いています。
一方で、技能実習や特定技能は「現場での実践」がメインのため、即戦力となる外国人を求める介護事業者に適しています。
ただし在留期間の制限があるため、外国人が帰国したあとの人材確保をどうするか、その点も踏まえておいたほうがいいでしょう。
なお、技能実習・特定技能1号に該当する外国人を5年経過後も雇用したい場合は、在留資格を変更することで雇用継続が可能です(条件あり)。
外国人介護人材に対して
どんな支援がある?
外国人の介護人材を受け入れる際には、以下のようなさまざまな支援を事業者側が行うことが求められます。
1.日本語教育の支援
外国人の介護人材が業務を円滑に行うためには、日本語能力の向上が不可欠です。
職員同士はもちろん、施設利用者ともコミュニケーションを取るときは日本語で話さなければならないため、日本語のスキルアップは欠かせません。
また、EPAや在留資格「介護」で採用された外国人は、いずれ介護福祉士の国家試験を受験するため、試験対策としての日本語教育も必須です。
他にも、介護業界の専門用語や施設のスタッフ内で通じる専門用語なども教えることで、外国人・日本人ともに円滑な介護を行えることが期待できます。
2.生活サポート
外国人が日本での生活に適応するための支援も重要です。住居の確保や行政手続きの支援、医療機関の紹介など、外国人が慣れない異国の地でもきちんと暮らしていけるように、生活全般にわたってサポートを行いましょう。
3.メンタルヘルスの支援
外国人にとって、慣れない異文化での生活や業務によるストレスは、想像以上に大きく重くのしかかるもの。場合によってはストレスを理由に早期帰国してしまうかもしれません。
そうしたストレスを軽減するため、受け入れ先の介護事業者は定期的なカウンセリングを行ったり、随時相談を受け付ける相談窓口の設置などを行いましょう。
また、常に外国人が相談しやすいメンターをつけるのも一つの方法です。
研修や実務で困っていること、対人関係などの悩みを聞いてアドバイスをしてくれたり、フォローしてくれたりする日本人スタッフをつけることで、安心するかもしれません。
4.在留資格変更の支援
技能実習や特定技能1号に該当する外国人は、条件を満たせば5年経過後も継続して雇用することが可能ですが、資格変更方法は主に3つのパターンがあります。
- 技能実習→特定技能へ移行する
- 特定技能→在留資格「介護」へ移行する
- 介護福祉士の国家試験に合格する
いずれの資格変更方法も、定められた実習や研修を修了していることが条件です。
特に技能実習の外国人は、年度によって技能実習1号・2号・3号を修了すること+5年以内に実務経験を積まなければいけないと定められています。
技能実習として受け入れて、いずれは介護福祉士の資格を取得してもらい長期雇用に切り替えたいと考える介護事業者は、そのための支援体制も整えておきましょう。
参照元:スキルド・ワーカー公式サイト(https://skilled-worker.jp/kaigo/kaigo-column/p1521/)
まとめ
少子高齢化が進む日本において外国人の介護人材を受け入れることは、介護事業者が抱える人手不足問題を解消し、施設利用者へのサービス品質向上につながる有力な手段です。
4つの制度から自社に合った仕組みを選び、適切な支援体制を整え、外国人が安心して働ける環境を作りましょう。
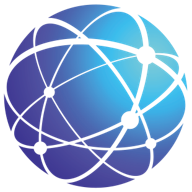 Global Talent Station
Global Talent Station

