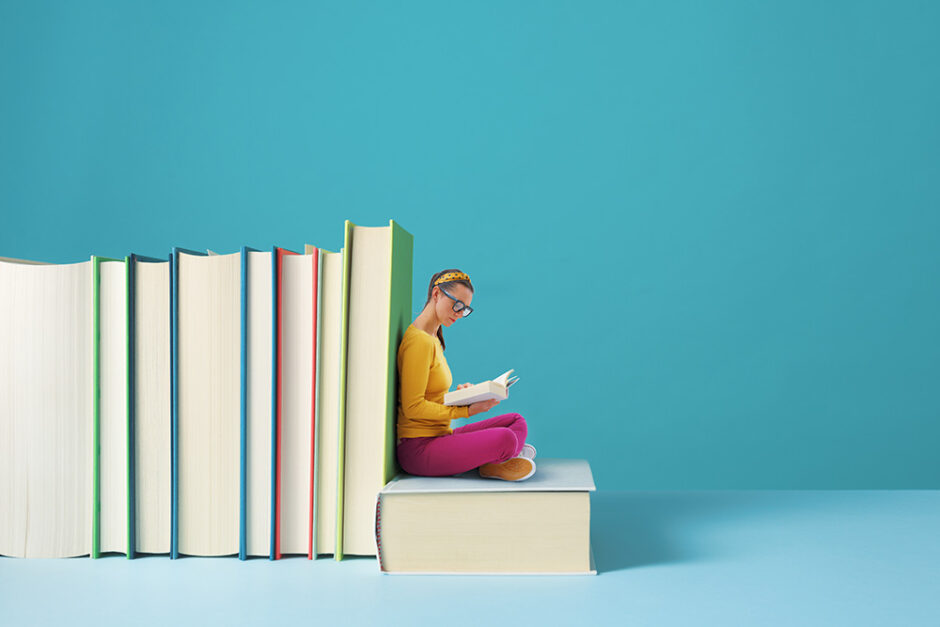日本の介護施設で外国人を雇用するには、内定から入社、さらに就業や離職、帰国に至るまで多くの手続きが必要です。ここでは、外国人を雇用する際に必要な手続きと注意点について、分かりやすく解説します。
採用内定から雇用までに
必要な準備と手続き
内定
「内定通知書」の作成は必須ではないため、作成して外国人労働者に渡すか否かは介護施設によって異なります。
内定通知書を作成する際は、外国人労働者の在留許可が下りず日本へ来られなくなった場合は「内定取り消し」になる旨を盛り込みましょう。
なお、内定通知書は作成しなくても労働条件通知書は作成必須です。
労働条件通知書には、賃金、就業時間、休日、福利厚生などの事項を記載します。
似たような書類で「雇用契約書」がありますが、両者の違いは以下のとおりです。
- 労働条件通知書…雇用主から外国人労働者へ一方的に「通知」するものなので、労使間の合意は不要
- 雇用契約書…雇用内容について、労使双方が確認・合意したことを証明する書類
内定通知書、労働条件通知書、雇用契約書のいずれにおいても、日本語だけでなく外国人労働者の母国語でも作成したものを渡しておくと、認識違いによるトラブルが起きにくくなります。
在留資格認定証明書の交付申請
外国人が日本で就労するには、入国管理局で在留資格認定証明書の申請を行います。
申請は雇い入れる介護施設の職員でも手続きができるため、職員が代理で申請するケースが多いようです。
申請の際に提出する書類は外国人労働者の在留資格によって異なりますが、介護に該当する場合は以下の書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書…1通
- 写真(縦4cm×横3cm、正面向きで顔がわかり、申請日より前の6ヶ月以内に撮影されたもの)…1枚
- 返信用封筒(宛先の記載および簡易書留用郵便切手の貼付必須)…1通
- 介護福祉士登録証の写し…1通
- 労働条件通知書…1通
- 外国人労働者が働く介護施設の概要(沿革、役員、組織、事業内容など)が分かる書類…1通
- 技能移転に係る申告書(過去に「技能実習」の在留資格をもって在留していたことがある場合のみ)
参照元:出入国在留管理庁(https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html)
ビザの取得
在留資格認定証明書が交付されたら、次はビザの取得手続きを行います。
- 介護施設の人事担当者などが、外国人労働者に在留資格認定証明書を送付。
「その外国人労働者が日本でどんな業務を行うか」が分かる資料も一緒に送る - 在留資格認定証明書を受け取った外国人労働者が、その原本と各種申請書、パスポートのコピーを持って現地の日本大使館へ赴き、ビザ取得の手続きを行う
ここで注意したいのは「提出された書類に不備がある場合はビザ発行が遅れてしまう」こと。
在留資格認定証明書は発行後3ヶ月以内に日本へ入国しなければいけませんが、ビザ取得用の書類不備で発行が遅れると期限内に日本へ入国できなくなる可能性があります。
訪日・在留カードの交付
ビザ発行後、外国人労働者が無事日本に入国できたら、空港で在留カードを交付してもらいます(※)。このカードは外国人が日本で生活し、働く上で必要な身分証明書であり、常に携帯する義務がある重要なカードです。
(※)在留カード交付ができる空港は羽田・成田・関西など7ヶ所です。それ以外の空港を利用して入国した場合は、日本での住所を届け出てから外国人労働者宛に在留カードが送付されます。
転入届
外国人労働者の住む場所が決まったら、14日以内に自治体へ転入届を出さなければなりません。転入届が受理されると住民票も取得できるようになり、日本国内での銀行口座開設や携帯電話契約など各種手続きがスムーズに進められます。
また、転入届受理後はマイナンバーカード通知書が外国人労働者宛に後日郵送されます。この通知書は社会保険加入時に必要な情報なので、外国人労働者には決してなくさないように念押ししておきましょう。
雇い入れ
外国人労働者の雇い入れは、日本人と同じように社会保険加入の手続きが欠かせません。それに加えて外国人労働者だけが対象となる手続きが外国人労働者の雇用状況の届出です。
この届出は法律で義務付けられているため、忘れないようにご注意ください。
就業時の手続き
在留期間の更新
外国人労働者の在留資格には期限があるため、更新時期が来たら外国人労働者が住む自治体を管轄する出入国在留管理官署にて申請を行います。
更新の申請は在留期限の3ヶ月前から可能ですが、申請に不備があると手続き完了のタイミングが遅くなります。期限までに更新できなかった場合は外国人労働者が不法滞在となってしまうため、期限日は必ずチェックしましょう。
年末調整
外国人労働者も日本人と同様に年末調整を行いますが、母国の家族に仕送りをしている外国人労働者の場合、扶養控除を受けられることがあります。
扶養控除を受けるには、外国人労働者の親族関係書類および仕送りをしていることが分かる書類を提出・提示が必要なので、そのことを外国人労働者に説明しましょう。
配置転換、転籍出向
外国人労働者の配置転換や転籍出向を行う場合は、在留資格を必ず事前に確認してください。
外国人労働者は許可された在留資格によって就労可能な業務や労働条件などが決まっています。雇用契約が変更される際、変更後の条件が現在の在留資格に適合していないと不法就労になってしまう恐れがあるのです。
外国人労働者だけでなく、介護施設側も事業所ごとの人員配置基準や外国人労働者の支援計画の見直しが発生する点にご注意ください。
離職時に必要な手続き
雇用状況の届出
外国人労働者が退職した場合、雇用主は14日以内に雇用状況の変更を出入国在留管理官署へ届け出ます(オンラインまたは書面のどちらでも可能)。
併せて雇用保険の手続きも行ってください。
所属機関等に関する手続き
実は外国人労働者も、退職後14日以内に労働契約が終了したことを出入国在留管理官署へ届け出ることが義務付けられています。
外国人労働者が期限内にきちんと届け出て手続きを行えるように、雇用主は離職手続きの際にきちんと説明しておきましょう。
帰国時に必要な手続き
厚生年金保険の脱退一時金
外国人労働者が帰国する場合、厚生年金保険の脱退一時金を請求することができます。この手続きには、脱退一時金の請求書やパスポートのコピー、銀行口座情報が必要です。
日本国内での手続きが難しい場合は帰国後に手続きを進めることも可能ですが、出国後2年以内に行わないと資格喪失となり、請求できません。
退職所得の選択課税による還付のための申告
厚生年金保険の脱退一時金を受け取る際は20.42%の税金が源泉徴収されます。日本国内在住であれば退職所得控除などの優遇措置を受けられますが、日本から出国した外国人労働者には適用されません。
代わりに「退職所得の選択課税による還付の申告」を行うことで、源泉徴収された税金の還付を受けられる可能性が高まります。
こちらも手続きが煩雑なので、外国人労働者が混乱したり損したりしないようにフォローしましょう。
まとめ
外国人労働者の雇用には、採用から入社、就業、離職、帰国に至るまで、多くの手続きが必要です。適切な時期に適切な手続きを行い、外国人労働者が安心して働ける環境を整備しましょう。
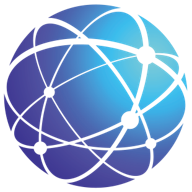 Global Talent Station
Global Talent Station