介護業界における人手不足は深刻な課題で、外国人労働者の活用は課題解決策の一つとして注目されています。しかし、訪問介護分野においては外国人労働者が十分に活躍できていない理由をご存知でしょうか。
ここでは、外国人労働者が訪問介護で活躍できない理由と、今後訪問介護で外国人労働者が活躍できるようになるためのポイントをご紹介します。
訪問介護で特定技能が活用されない理由
2025年1月時点、日本では「特定技能」の在留資格を持つ外国人労働者が訪問介護の業務に就くことが認められていません。
その理由は「日本での暮らしがまだ短い外国人労働者が、高齢者とのコミュニケーションを取ることや日本の生活習慣・文化などを理解することが難しいから」です。
訪問介護は利用者の自宅へ出向いてケアを行いますが、施設でのケアと大きく違うのはケアを行うスタッフと利用者が1対1で接するということ。
ときには利用者の家族ともコミュニケーションを取るため、その場合は1対2や1対3など、ケアを行うスタッフが1人で対応する人数が増えます。
またケアを行うスタッフが1人ということは、介護中の作業工程だけでなく利用者からの質問、要望などにも自分だけで適切に判断して対応しなくてはいけません。
このような理由を踏まえ、訪問介護分野での外国人労働者の活用には慎重な姿勢がとられてきました。
その反面、昨今は訪問介護の人手不足が深刻化しているのも事実です。
厚生労働省が公表したデータによると、介護サービス職員に分類される職種のうち、最も多く人材不足と感じているのが「訪問介護員」の80.6%でした(2023年7月時点 ※)。
訪問介護サービス職員の有効求人倍率も、2013年は3.29倍だったのが2022年には15.53倍にまで増加しているのです(※)。
(※)参照元(PDF):厚生労働省 訪問介護(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001123917.pdf)
特定技能が訪問介護分野で解禁!?
訪問介護分野の深刻な課題解消に向けて、近年、「特定技能」を訪問介護分野に適用する方針が議論されています。
2024年6月に開催された厚生労働省の審議会では、早ければ2025年春から特定技能の在留資格(※)を持つ外国人労働者に対して、訪問介護業務の対応が認められる方針が打ち出されました。
※特定技能の在留資格…特定技能1号、技能実習、EPAの介護福祉士候補者。
在留資格「介護」は、すでに訪問介護業務での就労が認められています。
特定技能外国人労働者が訪問介護業務に従事するためには、以下の条件を満たすことが求められます。
- 日本語能力試験(N3以上)の合格
- 介護職員初任者研修の修了
- 必要な研修の受講(訪問介護関連の業務、利用者やその家族とのコミュニケーションの取り方、日本の生活様式など)
- 一定期間のOJT
これにより、外国人労働者が日本語能力や介護スキルを十分に習得した上で訪問介護に従事することが期待できます。
参照元:厚生労働省 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会中間まとめ(案)(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001265042.pdf)
特定技能人材を訪問介護事業に
受け入れるときの課題
特定技能の外国人労働者を訪問介護事業で受け入れることは、人手不足解消の期待ができる反面、新たな課題が生まれる可能性があります。
利用者とのコミュニケーションや対応スキル
訪問介護は利用者と密接に関わるため、適切なコミュニケーション能力が必要です。しかし、外国人労働者が日本語を十分に話せなかったり理解できなかったりすると、利用者の要望や感情を理解することが難しくなります。
また、外国人労働者が母国と日本の文化的な違いを十分に理解できず、利用者との関係構築に影響を与える可能性もあるでしょう。
自動車の運転
訪問介護は利用者の自宅を訪れてケアを行う業務なので、地域によっては自動車の運転が不可欠です。そのため外国人労働者が運転免許を取得していない場合は、免許取得が優先課題となります。
母国で運転免許を取得していても、そのままでは日本での運転が認められない場合、免許切替や追加試験を受ける手続きが必要です。また、母国と日本の交通ルールの違いが理解できていないと事故につながるリスクが高まります。
この課題に対処するために、介護施設側では外国人労働者の免許取得や切替のサポート、交通安全研修などを計画して行うことが重要です。
受け入れ体制構築
訪問介護業務で外国人労働者に活躍してもらうには、介護施設側の受け入れ体制構築が重要です。
受け入れ体制は、以下の点をメインに構築すると良いでしょう。
- 日本語学習支援(オンライン自主学習環境の提供、定期的な日本語能力テストの実施など)
- 異文化理解支援(地域行事への参加など)
- メンター制度導入(日本人スタッフが指導・相談役としてサポート)
- キャリアアップ支援(介護福祉士などの資格取得支援、管理職へのステップアップ支援など)
- 生活環境の整備(住居確保、各種行政手続き、医療機関受診などのサポート)
- 新しい機器やシステム導入による業務効率化
上記の点は、特定技能の外国人労働者が訪問介護業務に就くために厚生労働省が介護施設へ求めている5要件(研修実施、OJT、キャリアアップ計画、ハラスメント対策、ICT活用)を満たすために欠かせません。
また受け入れ体制には、現場スタッフとの協力体制を築くことも含まれます。
現場でのサポート役として、日本人スタッフが外国人労働者の相談に乗る体制を整えることで、働きやすい環境が実現できます。
まとめ
特定技能人材の活用は、訪問介護事業における人手不足解消のきっかけとなる可能性があります。現状では制度的な制約や運用上の課題が存在し、なかなか解決に至っていませんでした。
しかし、国も本格的に課題解決に向けて方針を打ち出したことで、外国人労働者の活躍の場が広がり人手不足も解消されることが期待されます。
訪問介護事業を展開している介護施設は、外国人労働者の受け入れ体制の整備を進めましょう。
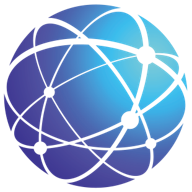 Global Talent Station
Global Talent Station

